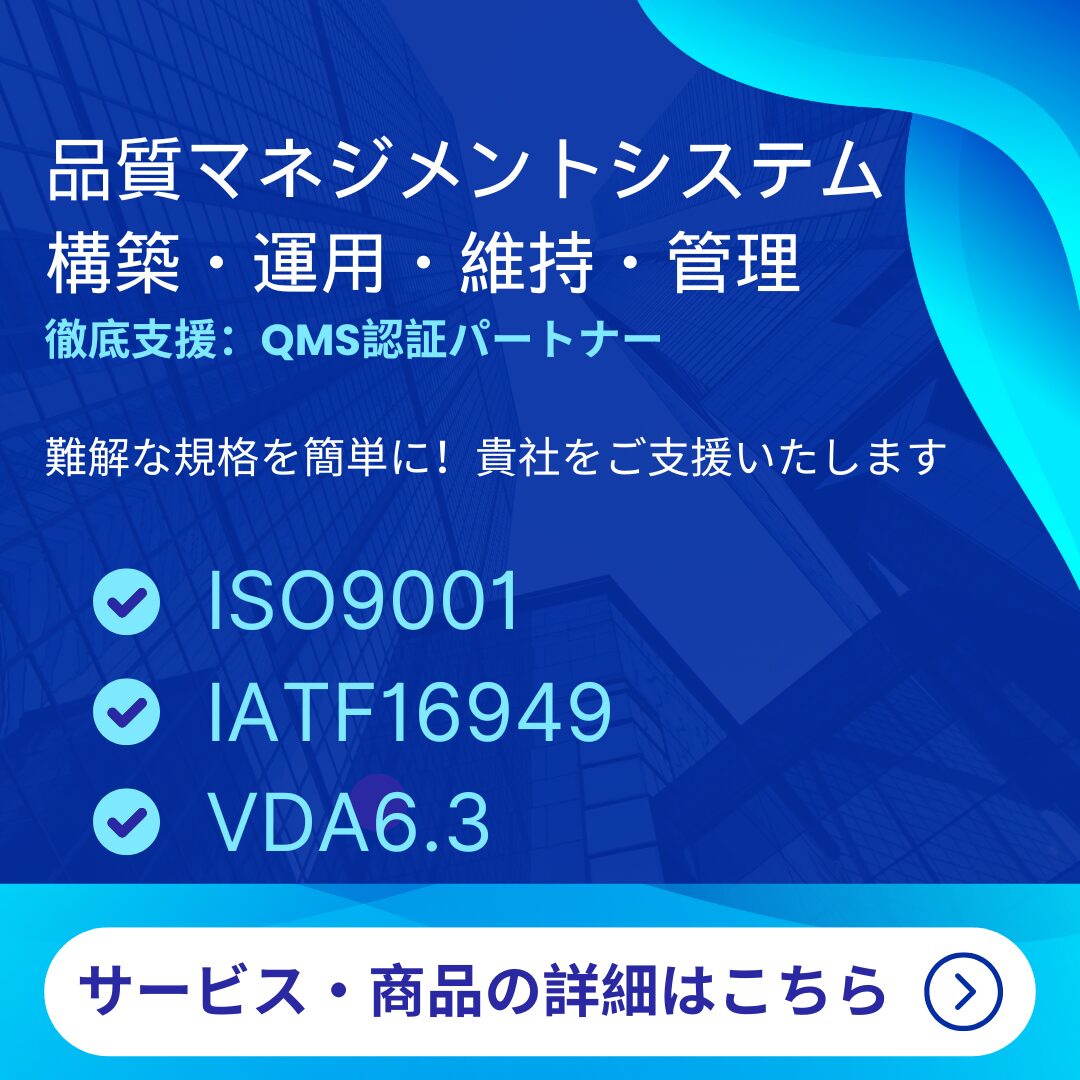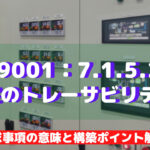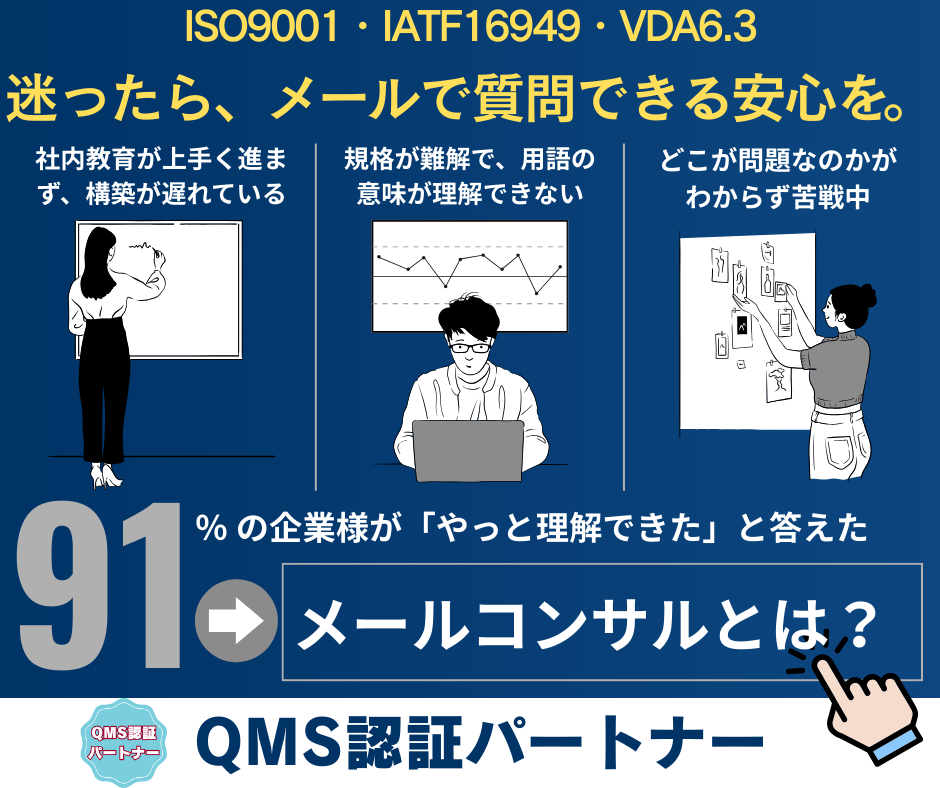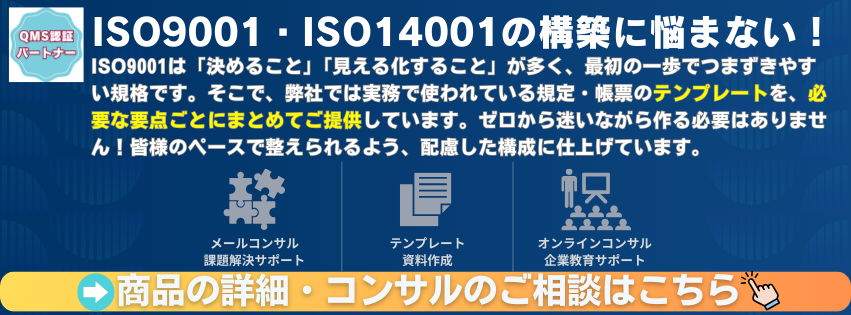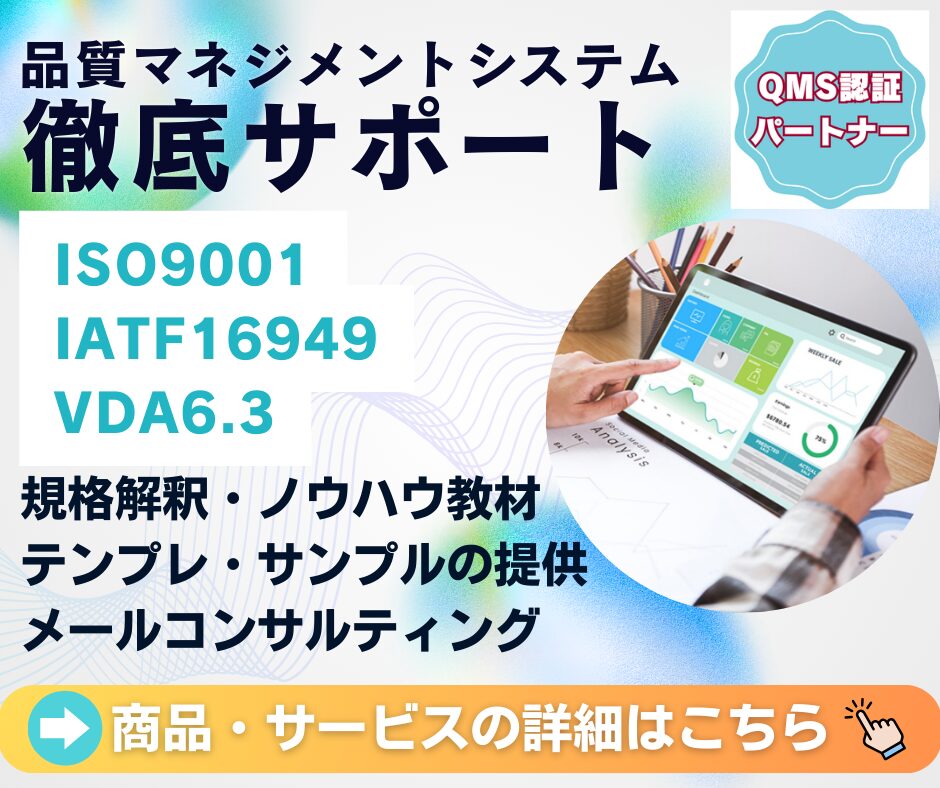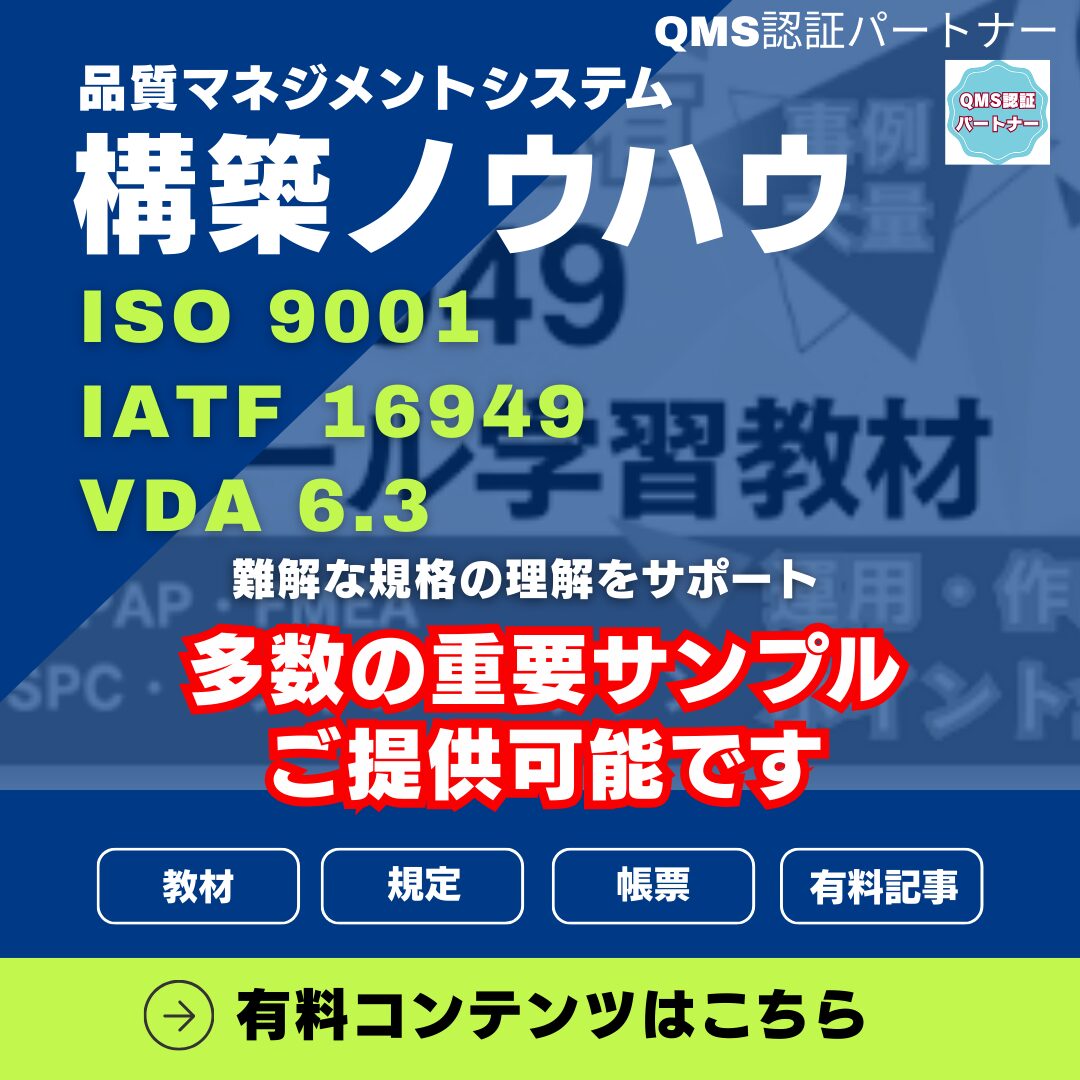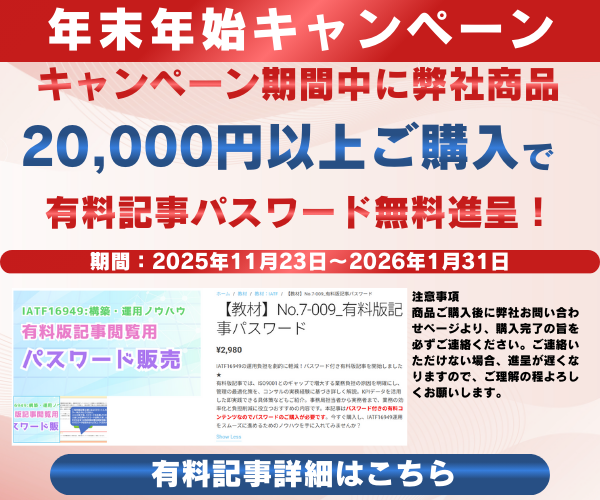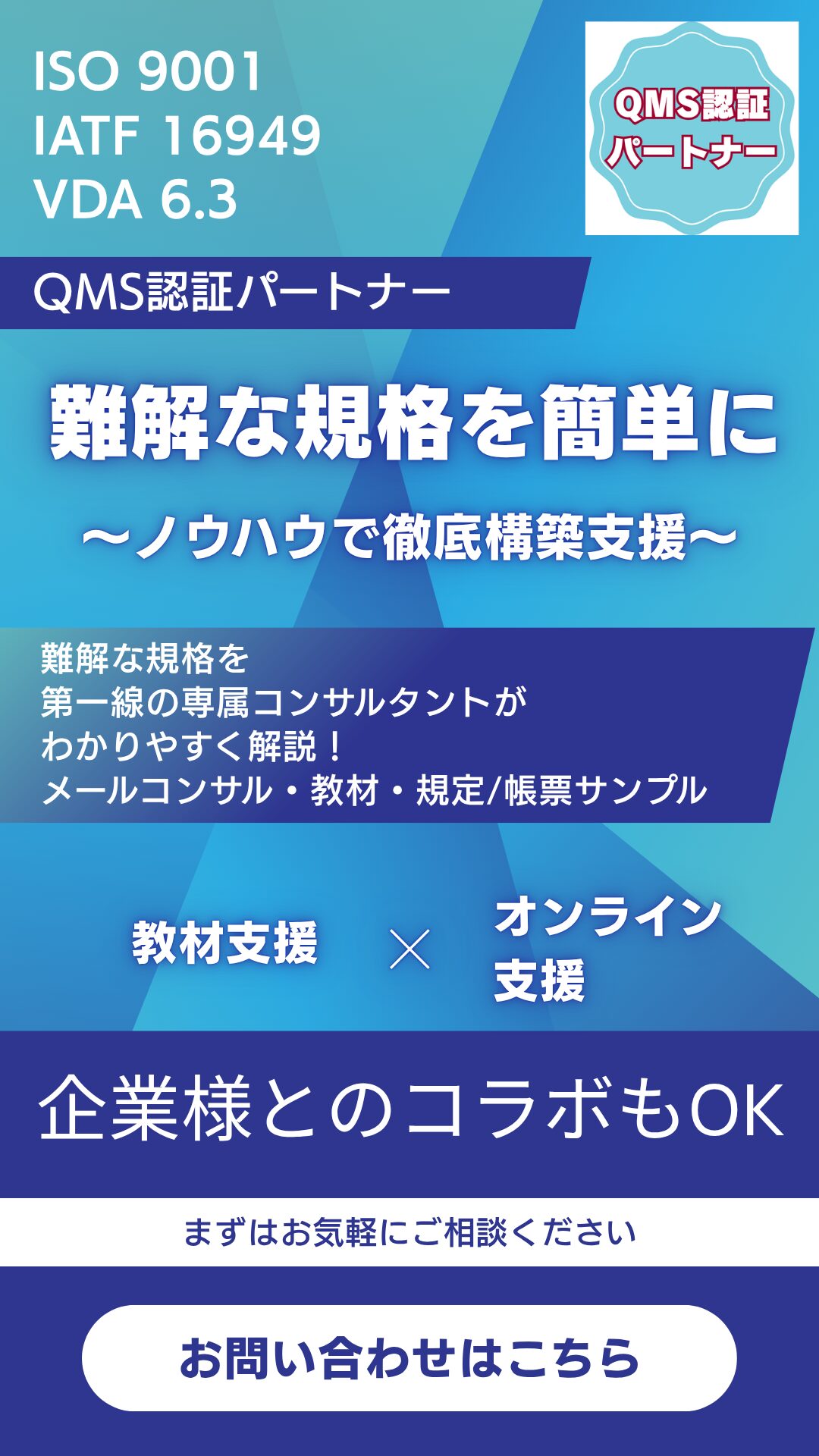ISO9001の基準に準拠し、品質管理に不可欠な校正プロセスとその重要性に焦点を当てたこの記事では、特に測定結果の不確かさと確からしさの理解を深めていただければと考えています。
社内外での校正作業の構築方法から、校正の基本定義、不確かさの概念とその品質保証への貢献、具体的な事例と評価方法まで、校正が組織の品質管理システム全体にどう組み込まれるかを詳しく解説していきます。
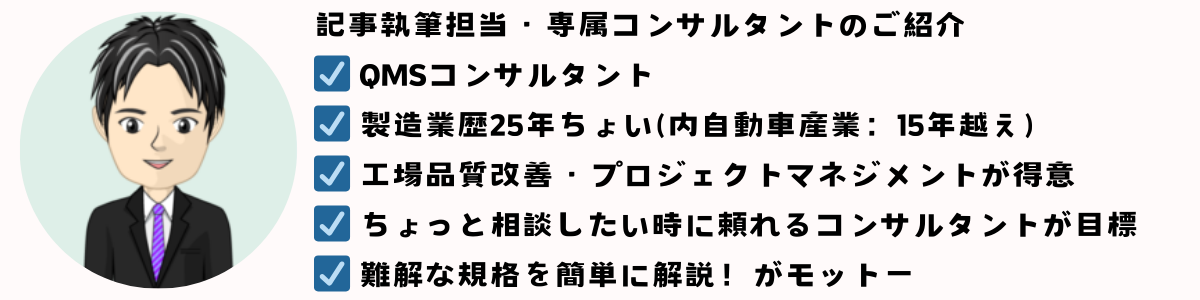
品質マネジメントシステム普及の応援が目的のサイトです!「難解な規格を簡単に解説」をモットーに、「ちょっと相談したい」ときに頼りになるコンサルタントを目指しています!まずはお気軽にご連絡ください★
「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!
✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ
👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!
✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ
✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む
✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック
✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ
👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!
✔ コンサルティングで具体的な課題を解決
✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入
✔ より実践的な学習教材でスキルアップ
皆様の目的に合わせて活用可能です!
| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |
2025年:新企画始動告知!
メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★
サービス詳細はこちら
・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について
【現在の空き状況:2025年9月現在】
・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ空きあり
・夜間:19:30-21:00でご相談承ります
・土日:少々空きあります
オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら
ISO9001の構築・運用のコツは「規格の理解」と「ルールと記録の構築」の2つがカギ!教材とサンプルを利用しつつ、相談しながら低コストで対応可能なノウハウをご提供いたします!
【ISO9001:おすすめ教材】
| 👑 | 教材No. | タイトル:詳細はこちら |
| 1 | No.3-001 | ISO9001学習支援教材 |
| 2 | No.9121 | 顧客満足度調査表 |
| 3 | No.72-1 | 個人の力量と目標管理シート |
○:お振込・クレジットカード払いが可能です。
○:請求書・領収書の発行は簡単ダウンロード!
→インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者の登録番号も記載しています。
○:お得なキャンペーン情報などは本記事トップをご確認ください。
この記事の目次
ISO9001と校正の基本と重要性

ISO9001は、組織が一貫して顧客および適用される規制要求事項を満たすために必要な品質管理システム(QMS)を確立、実施、維持、および継続的に改善するための国際標準であり、この標準は、効果的な品質管理の枠組みを提供し、顧客満足度の向上、運用の効率化、および組織の継続的な改善を促進します。
ISO9001における校正の役割と重要性について、以下の三つの点から解説します。
品質保証と顧客満足
校正は、測定機器やテスト機器が正確かつ信頼性のある結果を提供することを保証するプロセスです。
ISO9001は、製品やサービスが顧客の要求および適用される法的および規制要求事項を満たしていることを保証するために、正確な測定が不可欠であることを強調しています。
したがって、校正は品質保証の重要な要素であり、顧客満足の向上に直接貢献します。
校正は「品質管理システム」の一部
校正プロセスは、品質管理システム全体の一部として適用されていなければならずISO9001は、組織が使用するすべての測定機器を識別し、その校正または検証を計画し、実施し、記録することを要求しています。
これにより、製品の品質と安全性を検証し、プロセスの制御と改善に必要な正確なデータを提供することができるようになります。
校正の基本的な定義とプロセス
校正は、「測定標準との比較結果」と「不確かさ」を与える行為と定義されています。これにより、測定機器の精度と性能を評価し、必要に応じて調整を行うことができます。
校正プロセスには、適切な測定標準を選択すること、比較測定を行うこと、結果を記録し分析すること、および測定機器の調整または修正を行うことが含まれます。
また、校正証明書には測定結果の不確かさが記載されることが重要であり、これがトレーサビリティの根拠となります。
以上より、ISO9001における校正は、品質管理システムの効果的な運用と継続的な改善に不可欠あり校正により、組織は測定機器の正確性を保証し、製品とプロセスの品質を維持し、顧客満足を高めることができます。
関連記事
・面談不要、メールだけで完結
・初回は、1質問無料!納得してからご利用可能です
・月額プラン(サブスク形式)なら自動更新!何度でも安心相談可能!
【重要】校正の不確かさの意味と事例

それでは本記事の本題です。
校正の不確かさとは、測定結果に伴う疑わしさの度合いを定量化したものです。これは、測定機器の性能、測定方法、環境条件、操作者の技能など、多くの要因によって影響を受けます。
不確かさを理解することは、測定結果の信頼性を評価し、適切な意思決定を行うために不可欠です。
以下に、校正の不確かさをわかりやすく説明するための事例を示します。
事例:温度計の校正
ある製造業で使用されている温度計を例にとって説明いたします。
この温度計は、製品の品質を保証するために正確な温度測定が必要です。同社の製品に対する安全基準では、温度が特定の範囲内であることが求められています。
この温度計を校正する際、不確かさの概念が重要になります。
校正プロセスと不確かさの評価
次に温度計の不確かさの評価ステップを見ていきましょう。
| ステップ | 内容 |
| 標準との比較 | 温度計を既知の正確な温度を提供する標準器(たとえば校正用の温度バス)と比較します。標準器の温度は、20.00℃と示されていました。 |
| 測定と読み取り | 温度計を使用して温度を測定し、その読み取り値が20.05℃であることを確認しました。 |
| 不確かさの評価 | 不確かさの評価には、温度計の精度、標準器の不確かさ、測定環境(温度、湿度など)、測定に関わる人的要因などが考慮されます。この例では、全体の不確かさを±0.05℃と評価しました。 |
| 【重要】不確かさの意味とその影響 この温度計の校正における不確かさが±0.05℃であることは、測定値が実際の温度から最大0.05°C上か下にずれる可能性があることを意味します。 つまり、測定結果の真の値は、20.00℃から20.10℃の間、または19.95℃から20.05℃の間のどこかにあると推定されます。 |
この不確かさの情報があることで、製造業者は、製品の品質基準を満たしているかどうかをより正確に判断できます。例えば、製品が20℃±0.1℃の範囲内である必要がある場合、この温度計の不確かさを考慮に入れても安全基準を満たしていることがわかります。
この事例から、不確かさを適切に評価し、校正証明書に記載することが測定機器を使用して重要な品質保証決定を行う際の信頼性と正確性を高めるためにどれほど重要かが理解できます。
不確かさを考慮した校正プロセスの構築

不確かさを考慮した校正プロセスの構築は、社内での実施も外部の専門機関に依頼する場合も、品質管理システムの整合性と測定結果の信頼性を保証する上で重要です。
以下に、それぞれのシナリオにおける校正プロセスの構築方法を示します。
社内での校正(内部校正)プロセス構築
| ステップ | 内容 |
| 校正計画の策定 | 使用する測定機器のリストアップ、測定範囲、必要な校正頻度を決定します。機器ごとに校正プロセス、必要な標準器、参照される標準(例:国際単位系SI)を明確にします。 |
| 校正手順の開発 | 校正を行う具体的な手順を文書化します。これには、使用する標準器、測定条件(温度、湿度など)、測定手順、不確かさの評価方法が含まれます。 |
| 標準器の管理 | 使用する標準器が適切に校正され、その校正が有効であることを確認します。標準器自体の不確かさも考慮に入れます。 |
| 校正実施 | 手順に従って校正を実施し、測定値と標準器の値との比較を行います。 |
| 不確かさの評価 | 校正過程で生じうる全ての不確かさの要因を特定し、それらの合成不確かさを計算します。 |
| 記録と報告 | 校正結果と不確かさの評価を詳細に記録し、内部校正証明書を作成します。 |
| レビューと改善 | 校正プロセスを定期的にレビューし、必要に応じて改善を行います。 |
【補足】不確かさの計算方法
計測機器の不確かさを計算する際には、一般的に次のような手順に従います。不確かさには「標準不確かさ」と「合成標準不確かさ」があり、それぞれ以下の計算式を用います。
①標準不確かさ(Standard Uncertainty)
標準不確かさは、計測値のばらつきや機器の特性に基づく不確かさを表します。
A類の標準不確かさ(UA)
経験的なデータから得られる標準偏差を用いて計算されます。
s:測定結果の標準偏差
n:測定の回数
B類の標準不確かさ(UB)
製造者の仕様や機器のカタログデータ、あるいは標準的な参照データから得られる不確かさを基に計算されます。分布が均一である場合、次の式がよく使われます。
a:仕様から得られる誤差範囲
②合成標準不確かさ(Combined Standard Uncertainty)
合成標準不確かさは、複数の不確かさが独立している場合に、それらを組み合わせて算出します。合成標準不確かさUC
は次のように計算されます。
ここで、UAとUB
はそれぞれA類とB類の標準不確かさです。
③拡張不確かさ(Expanded Uncertainty)
実際の報告では、合成標準不確かさに拡張係数k
を掛けた「拡張不確かさ」が用いられることが一般的です。
k:拡張係数(通常は2または3が使用されることが多い)
U:拡張不確かさ
この計算により、不確かさの範囲が一定の信頼度で表されます。これらの手順を適用して、計測機器の不確かさを計算することができます。
校正管理用教材のご紹介
| 帳票名 | 校正・検証管理表 | ||
|---|---|---|---|
| 納品形式 | ダウンロード | ||
| ファイル形式 | Excel:貴社にて自由にカスタマイズ可能です | ||
| 特徴 | 計測機器の管理を徹底サポート!校正・検証管理表、校正記録、計測機器・試験所管理規定で、計測機器全般管理の効率化を図りませんか?ISO/IATFのサンプル教材としてご活用いただけます。 | ||
| 詳細 | 商品詳細はこちら | ||
| 関連帳票 | No.71521_校正記録 | ||
| 関連規定 | No.7151_計測機器・試験所管理規定 | ||
外部の校正業者や専門機関を利用する場合
| ステップ | 内容 |
| 適格なサプライヤーの選定 | ISO/IEC 17025などの適用可能な国際標準に準拠して認定された校正業者を選定します。 |
| 要件の明確化 | 校正業者に対して、測定機器の種類、測定範囲、求める不確かさのレベル、任意の特定要件(例:環境条件)を明確に伝えます。 |
| サービスレベル契約(SLA)の締結 | 提供されるサービスの範囲、校正の頻度、報告形式、納期、費用などを定めた契約を結びます。 |
| 校正の依頼と機器の送付 | 校正が必要な測定機器を校正業者に送付します。機器を送付する際は、適切な梱包と輸送方法を選択して、機器が損傷しないようにします。 |
| 校正結果のレビュー | 校正業者から提供される校正証明書を受け取った後、結果と不確かさの評価を慎重にレビューします。校正証明書には、測定機器の識別情報、校正日、使用された標準器、測定結果、不確かさの評価、および校正を実施した業者の情報が含まれている必要があります。 |
ISO9001:校正の不確かさまとめ

不確かさを考慮した校正プロセスを構築する際は、社内での校正作業と外部業者による校正の両方で、品質管理の原則と最良の実践を適用することが重要です。
このプロセスを通じて、測定機器の信頼性と精度を保証し、組織全体の品質保証体制を強化することができます。
また、不確かさの慎重な評価と管理は、測定結果の信頼性を向上させ、より正確な意思決定を支援します。
組織は、これらのプロセスを継続的に見直し、改善することで、変化する要件や技術の進歩に適応し、品質管理の効率と効果を最適化することができます。
・教材(電子書籍)の教育教材
・規定類・帳票類のサンプルによる自力構築支援
・メールコンサルティング
最終的には「自社で回せる品質マネジメントシステム」を目指して、継続的な改善・運用が可能な体制の構築を目指します!