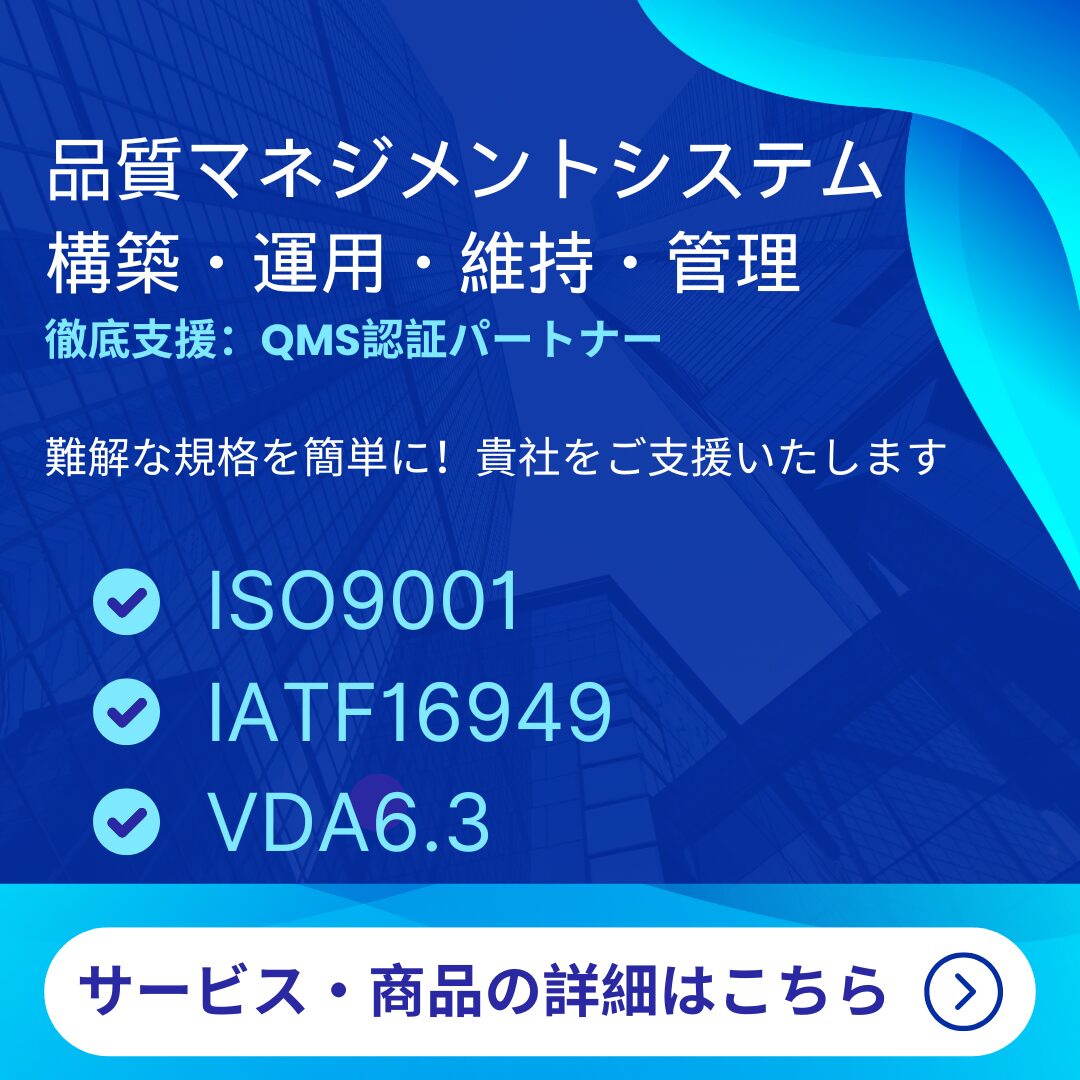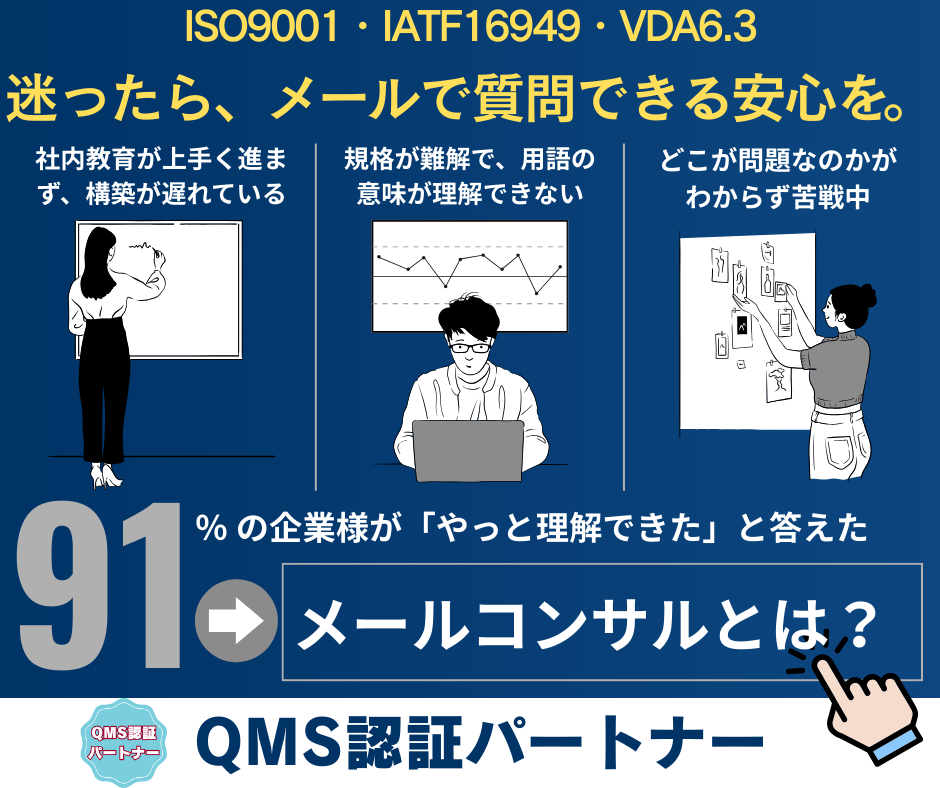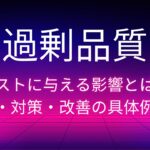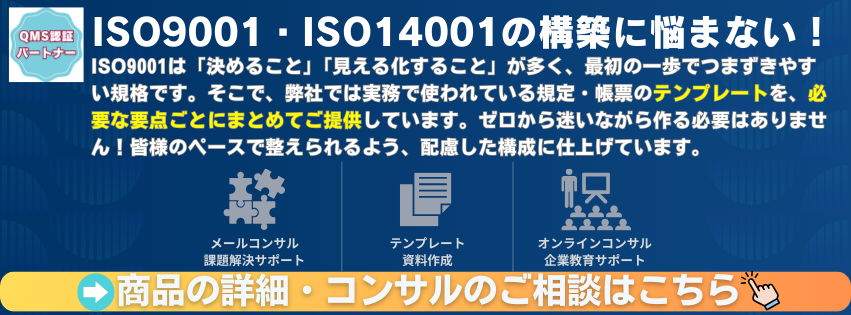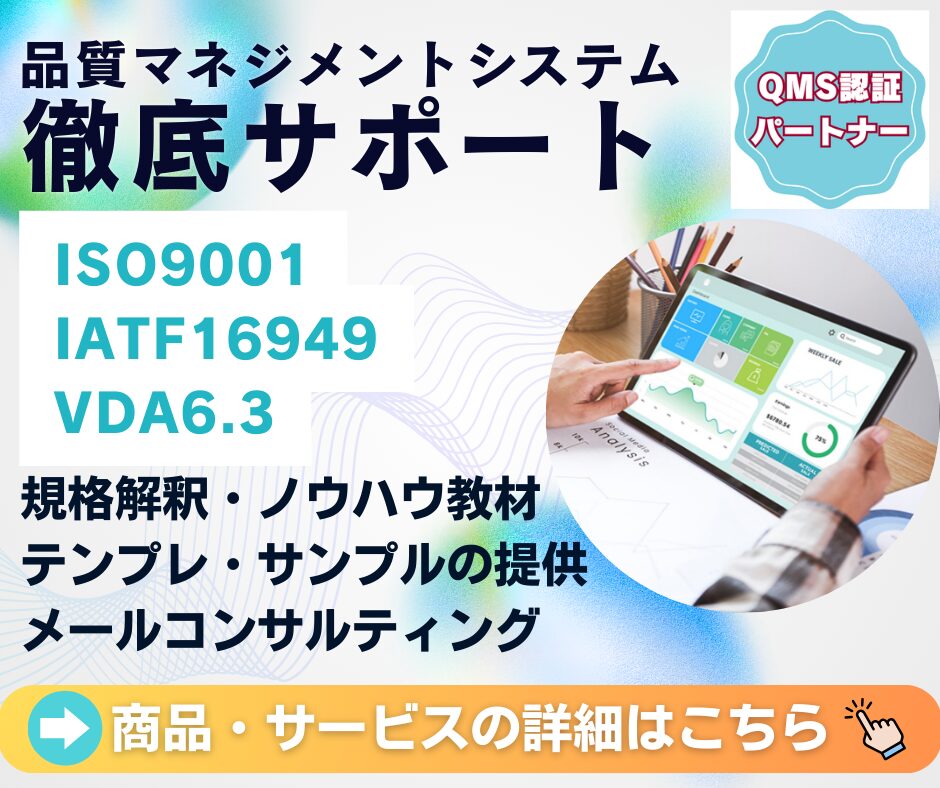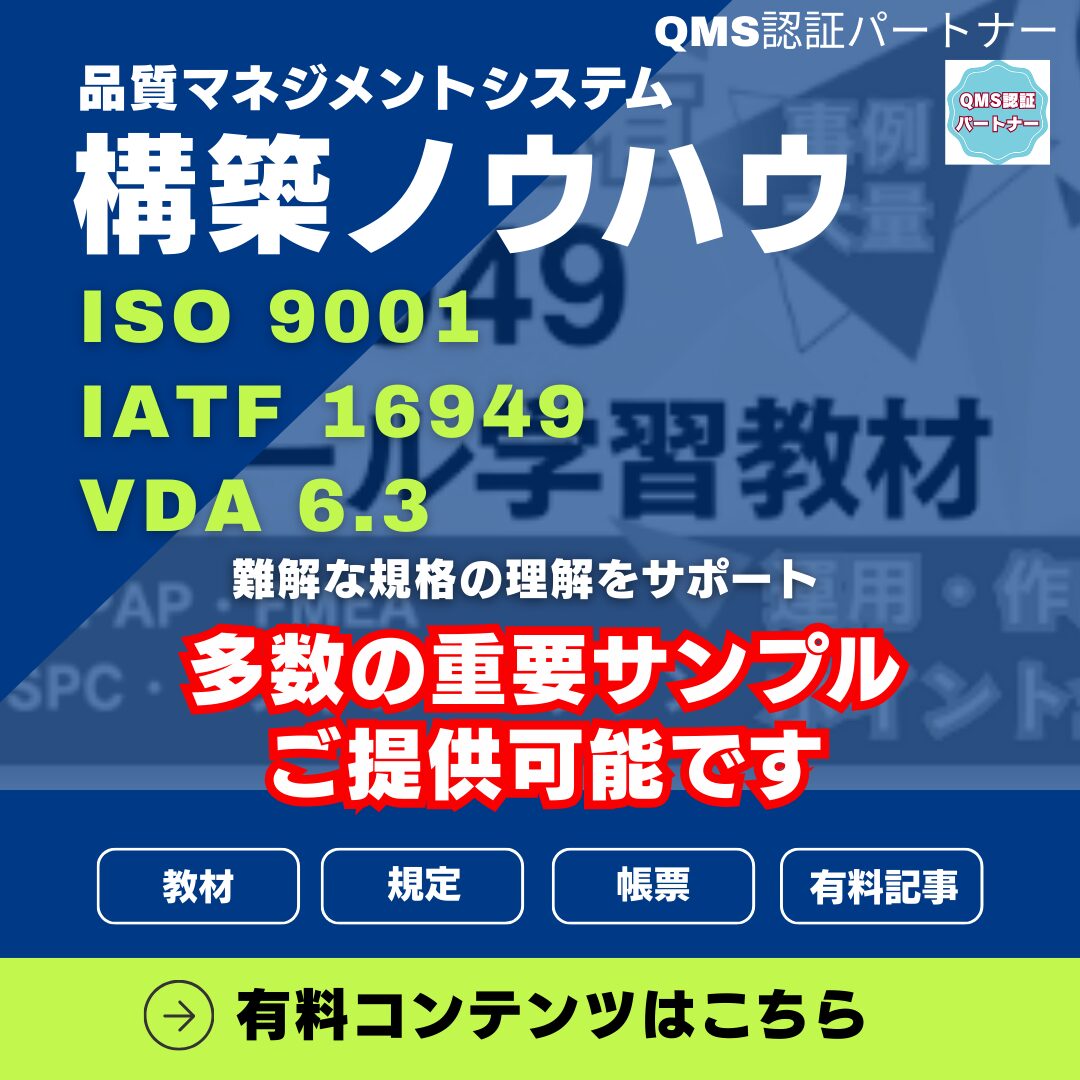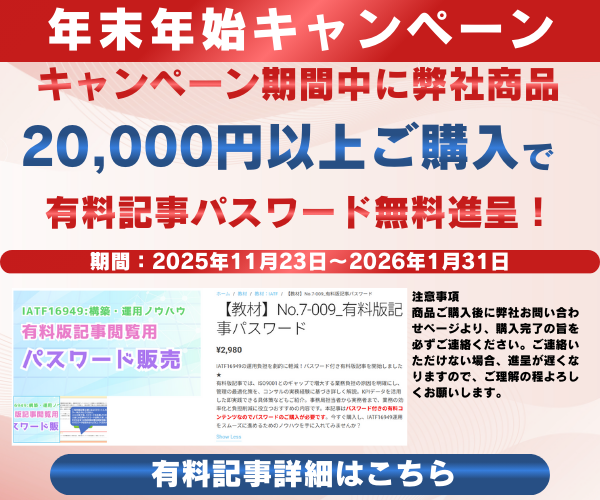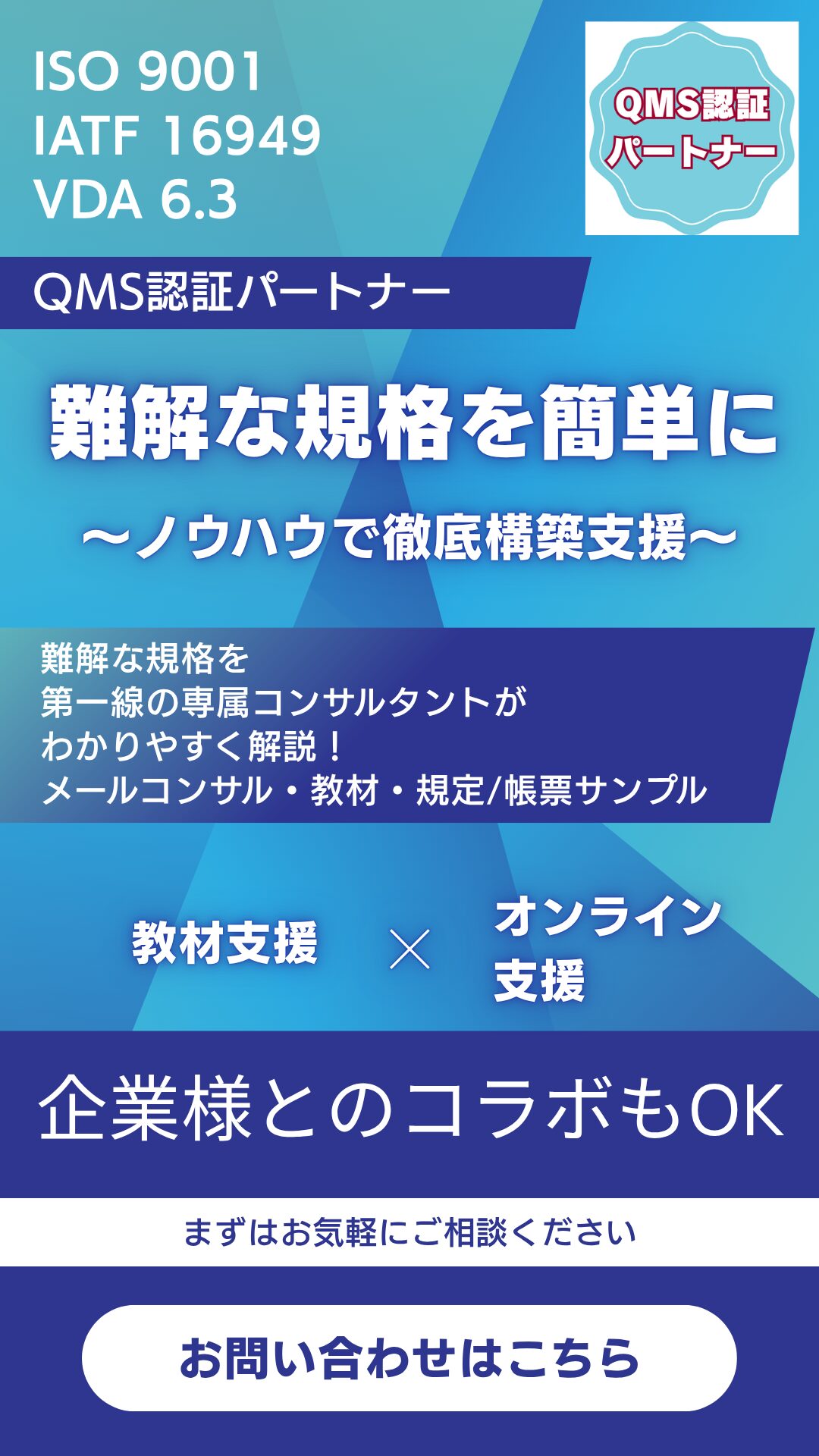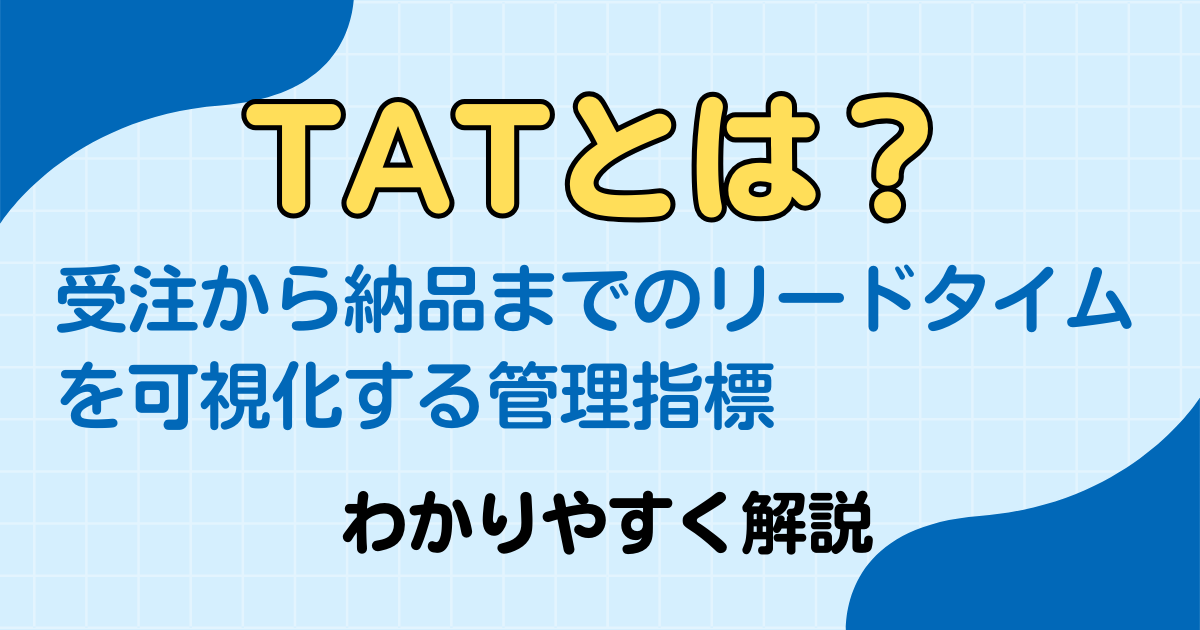
ビジネスのスピードがますます求められる現代において、「TAT(Turn Around Time)」という指標が注目を集めています。TATとは、受注から納品までにかかる全体の所要時間を示すもので、製造業や物流業はもちろん、ITやサービス業でも活用されている重要な管理指標です。この時間をいかに短く、かつ安定して維持できるかは、顧客満足度の向上や利益率の改善に直結します。
この記事では、TATの基本的な意味から、計算方法、改善策、運用上の注意点までを、わかりやすく解説します。
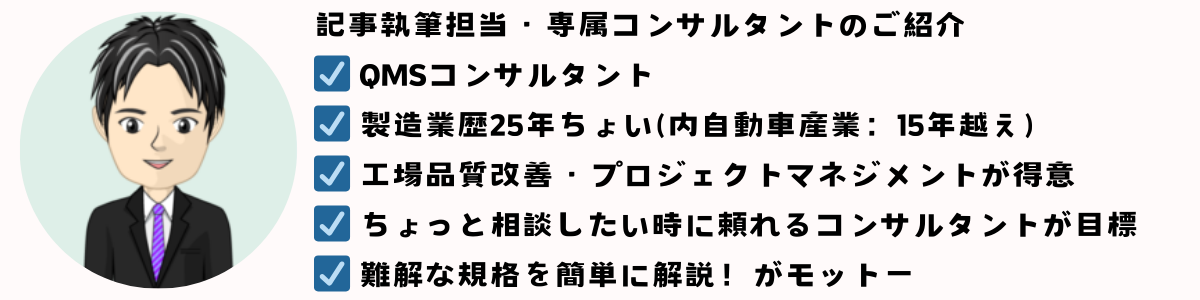
品質マネジメントシステム普及の応援が目的のサイトです!「難解な規格を簡単に解説」をモットーに、「ちょっと相談したい」ときに頼りになるコンサルタントを目指しています!まずはお気軽にご連絡ください★
「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!
✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ
👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!
✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ
✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む
✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック
✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ
👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!
✔ コンサルティングで具体的な課題を解決
✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入
✔ より実践的な学習教材でスキルアップ
皆様の目的に合わせて活用可能です!
| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |
2025年:新企画始動告知!
メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★
サービス詳細はこちら
・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について
【現在の空き状況:2025年9月現在】
・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ空きあり
・夜間:19:30-21:00でご相談承ります
・土日:少々空きあります
オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら
IATF16949の構築・運用のコツは「規格の理解」と「ルールと記録の構築」の2つがカギ!ISO9001とのギャップを埋める教材とサンプルを利用しつつ、相談しながら低コストで対応可能なノウハウをご提供いたします!
【IATF16949:おすすめ教材】
| 👑 | 教材No. | タイトル:詳細はこちら |
| 1 | No.1-001 | IATF16949+ISO9001学習教材 |
| 2 | No.2-001 | コアツール学習教材 |
| 3 | No.7-001 | IATF16949_内部監査概説_学習教材 |
○:お振込・クレジットカード払いが可能です。
○:請求書・領収書の発行は簡単ダウンロード!
→インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者の登録番号も記載しています。
○:お得なキャンペーン情報などは本記事トップをご確認ください。
この記事の目次
TATとは?基本概念と意味
まずはTATという言葉の意味から理解しましょう。
TAT(Turn Around Time)の定義と起源
TAT(Turn Around Time)とは、顧客からの注文を受けてから、製品やサービスが納品・提供されるまでに要する総所要時間を指す指標です。製造業では「受注から出荷まで」、IT業界では「システムへのリクエストから応答まで」など、業種によって対象となるプロセスは異なりますが、基本的には「プロセス全体の所要時間」を可視化するために使われます。
TATという概念はもともと航空業界や医療分野でも使われており、飛行機の整備にかかる時間や検査結果が出るまでの時間を管理する目的で活用されていました。そこから発展して、現在ではサプライチェーン全体の効率を測る共通指標として、多くの業界に浸透しています。
TATは単なる時間の測定ではなく、業務効率と顧客満足を両立させる上で欠かせない管理要素といえます。
リードタイムや納期との違いと関係性
TATと混同されやすい概念に「リードタイム」や「納期」がありますが、それぞれに明確な違いがあります。
リードタイム(LT)は、部品の調達や製造にかかる特定の工程の所要時間を指すことが多く、部分的なプロセス管理に焦点を当てます。
対してTATは、受注から納品までの全体フローを包括的にとらえる指標であり、営業・調達・製造・物流といった部門をまたいだ横断的な時間管理に用いられます。また、納期は「いつ納品するか」という顧客との約束の日時であり、TATとは目的が異なります。
つまり、TATはリードタイムや納期と密接に関係しながらも、より広い視点からプロセス全体を見える化するための指標です。これらの違いを正しく理解し、役割を分けて活用することが、的確な納期管理と業務改善の鍵となります。
おすすめ記事
TATが重視される理由と影響範囲
TATの短縮は、単なる業務改善ではなく、経営効果にも直結します。
顧客満足度・利益率・在庫コストとの関係
TATが短ければ短いほど、顧客が製品やサービスを早く受け取れるため、顧客満足度が向上します。特にBtoB取引では納品リードタイムが取引継続の判断基準となることもあり、TATは競争力を左右する指標の一つです。
また、TATの短縮により在庫の滞留が減り、保管コストや資金繰りの改善にもつながります。さらに、生産リソースの無駄が減ることで、利益率の向上という側面でも効果があります。
たとえば、不要な仕掛品を減らすことで原価管理がしやすくなり、部品や人材の配分も最適化されます。このように、TATは「単なる時間管理」にとどまらず、売上・コスト・信頼の3方向から企業経営にインパクトを与える指標として捉える必要があります。
IT・製造・物流など各業界におけるTATの活用事例
TATは特定の業界だけで使われるものではなく、さまざまな業種で重要な管理指標として活用されています。たとえば、製造業では「受注から出荷までの期間」をTATとして定義し、工程間の滞留時間やボトルネックを見える化することで、リードタイムの削減を図っています。
物流業界では、配送センターへの入荷から顧客への出荷完了までをTATと捉え、遅延発生箇所の特定や、システム改善の判断材料としています。
IT業界では、システム障害発生から復旧までの所要時間や、カスタマーサポートにおける問い合わせ対応時間などがTATの対象となり、サービス品質の指標として使われています。
どの業界でも「スピード」と「効率性」を可視化し、継続的な改善に役立てるためのツールとしてTATは活躍しています。
おすすめ記事
・面談不要、メールだけで完結
・初回は、1質問無料!納得してからご利用可能です
・月額プラン(サブスク形式)なら自動更新!何度でも安心相談可能!
TATの計算方法と構成要素
TATを正確に把握するには、分解して分析することが不可欠です。
TATの基本式と各プロセスの内訳
TAT(Turn Around Time)は基本的に、「納品日」−「受注日」=TATというシンプルな式で表すことができます。ただし、現場での改善や分析に活用するためには、この全体時間を複数のプロセスに分解して捉える必要があります。
たとえば、営業部門での見積もり・契約処理に要する時間、資材の調達リードタイム、製造の加工・組立時間、品質検査の待機時間、出荷準備や輸送時間など、一連の流れの中に複数の構成要素が存在します。それぞれのプロセスで発生している無駄や待機を見える化しなければ、TAT全体の短縮にはつながりません。
つまり、TATを管理するとは、単に合計時間を測定するだけでなく、各工程に潜む非効率の発見と改善に取り組むことを意味します。
可視化のポイントとKPIとしての使い方
TATは単に数値として記録するだけでは意味がなく、現場や経営層が“見て使える”形で可視化することが重要です。
たとえば、各プロセスの所要時間をガントチャートやプロセスマップで表すことで、どこで時間がかかっているかが一目で分かります。さらに、過去のTAT推移を時系列でグラフ化すれば、改善効果や変動傾向も把握しやすくなります。
また、TATをKPI(重要業績評価指標)として設定する場合は、単に平均値だけでなく、最大値やバラつきにも注目することが重要です。TATが長期化する傾向が見られれば、納期遅延や顧客不満のリスクにつながるため、定期的にモニタリングし、早期の対策を講じる必要があります。
可視化とKPI化によって、TATは「現場の改善指標」から「経営判断の武器」へと進化させていきましょう!
サプライチェーン全体での最適化施策
TATの短縮を本質的に進めるには、自社内の改善だけでなく、サプライチェーン全体を見渡す視点が欠かせません。たとえば、調達先の納期遅延や外注工程の待機時間がTATの長期化につながっている場合、自社の努力だけでは限界があります。そのため、調達先・協力会社・物流業者などと情報を共有し、全体としての流れを最適化する協働体制が重要になります。
具体的には、納期共有システムやEDIの活用、定期的な納期会議の実施、緊急時の代替ルート確保などが有効でありさらに、サプライチェーン全体の可視化によって、在庫削減や資源の最適配分も進めることができます。
TATを“自社の指標”から“連携の成果”へと発展させることが、真の納期短縮と顧客満足向上につながる鍵となります。
おすすめ記事
TAT管理の落とし穴と注意点
TATは便利な指標ですが、過信や誤用には注意が必要です。
「数値管理だけ」では不十分な理由
TATをKPIとして管理する際に陥りがちなのが、数値だけを追いかけてしまう「形式的な管理」です。TATの平均値や目標達成率ばかりに注目すると、プロセスの中で何が本当に起きているのかが見えなくなってしまいます。
たとえば、一部の部門で無理に短縮を図ることで、他の工程にしわ寄せが発生し、品質や安全性が犠牲になることもあります。また、数値が良好でも、現場では不満や混乱が広がっているケースもあり、現場の声や実態を反映しないTAT管理は持続性に欠けます。TATは「結果」としての指標であると同時に、「改善の入口」としての意味も持ちます。
よって、数値の背景にあるプロセスや人の動きにしっかり目を向け、定性情報とセットで運用することが、本質的な改善へとつながっていくといえます。
TATと他のKPIとのバランスの取り方
TATは重要なKPIのひとつですが、単独で評価してしまうと判断を誤るリスクがあります。
たとえば、TATを短縮するために製造スピードを上げすぎれば、品質KPIである不良率が悪化することがあります。また、在庫を極端に減らしてTATを改善しようとすれば、納期遵守率が下がるといったトレードオフも生じます。
TATを最大限に活用するためには、QCD(品質・コスト・納期)全体を見据えたKPI設計が不可欠であり具体的には、TATと納期遵守率、在庫回転率、工程稼働率などをあわせて管理し、相互に矛盾しない範囲でバランスを取る必要があります。また、部門間でKPIの意図や優先順位を共有し、部分最適ではなく全体最適を志向するマネジメントが求められます。
TATはあくまで全体の一指標として、他のKPIと連動させて使うことで真の効果を発揮します。
まとめ
TAT(Turn Around Time)は、受注から納品までの所要時間を可視化することで、企業の競争力を高める重要な指標です。単なる時間の記録ではなく、各工程の課題やボトルネックを発見し、全体最適につなげるための“改善の起点”となります。
TATの数値をKPIとして正しく活用し、他指標とのバランスをとることで、顧客満足と利益の両立が可能になるものなので、経営判断にもつながる指標だからこそ、本質を理解して運用することが成功の鍵となっていきます。
・教材(電子書籍)の教育教材
・規定類・帳票類のサンプルによる自力構築支援
・メールコンサルティング
最終的には「自社で回せる品質マネジメントシステム」を目指して、継続的な改善・運用が可能な体制の構築を目指します!