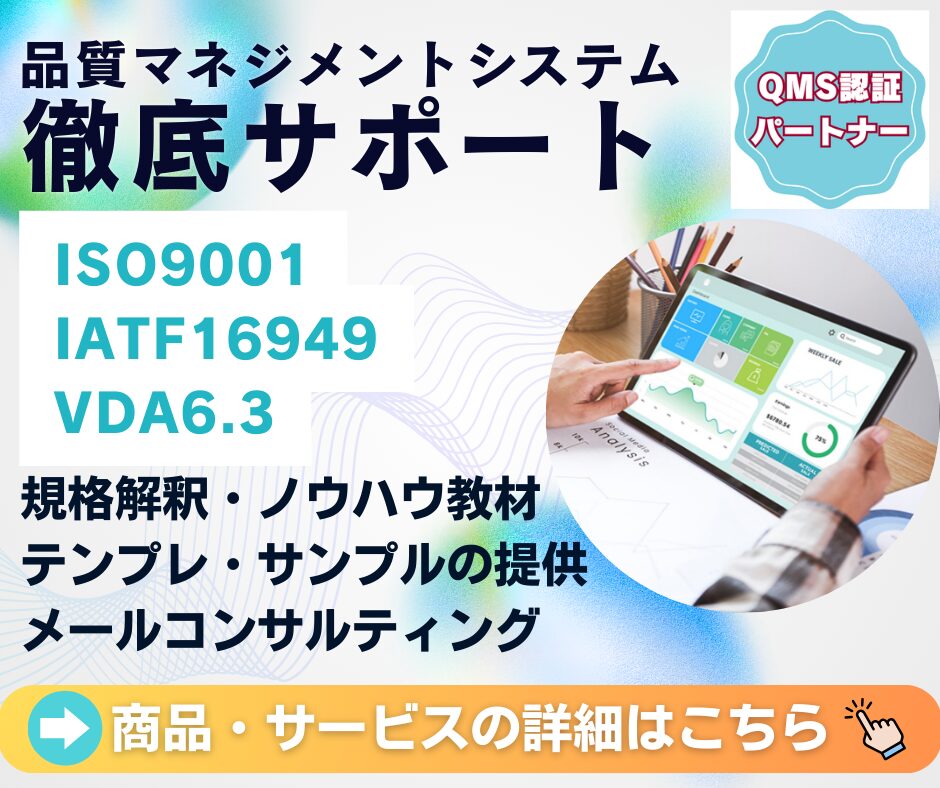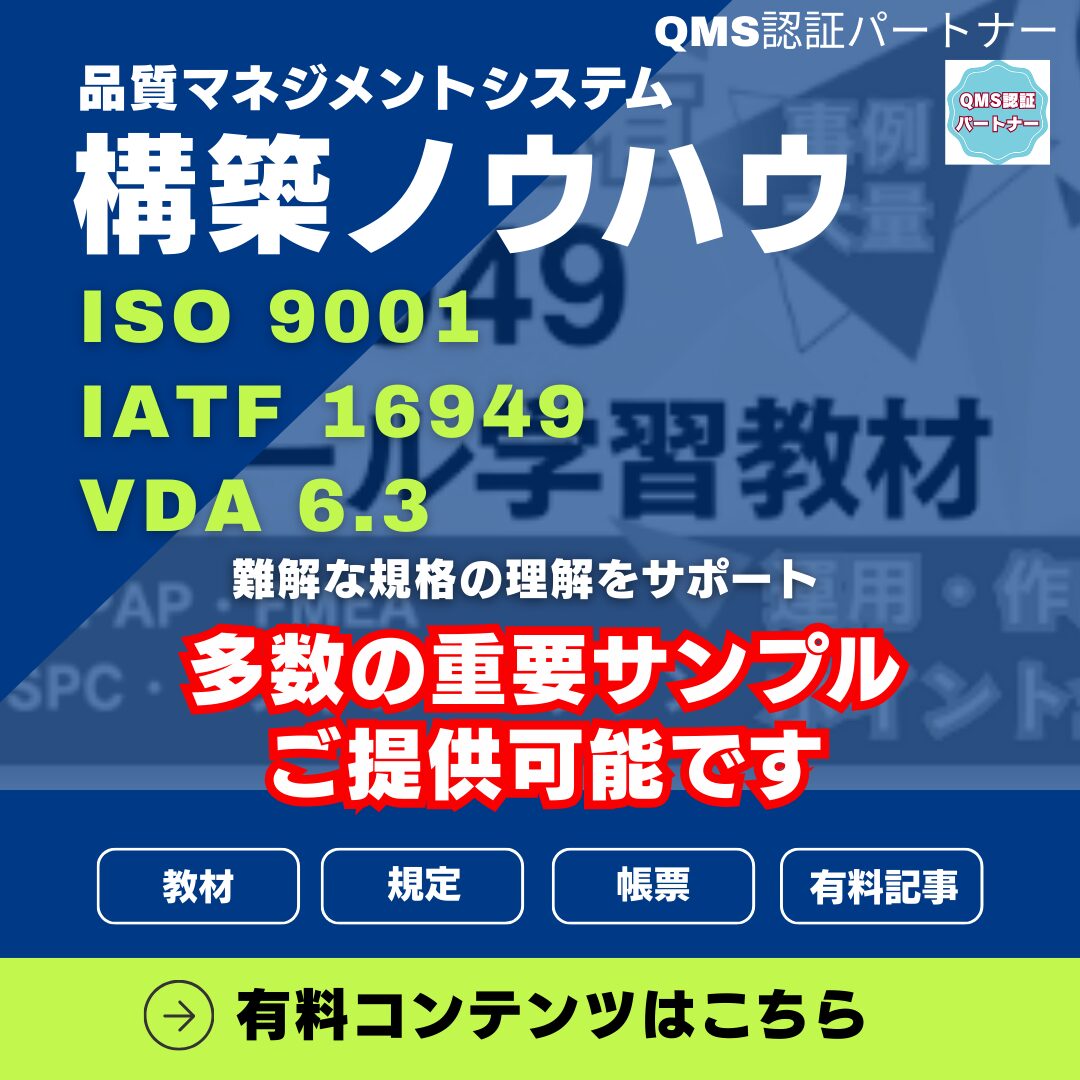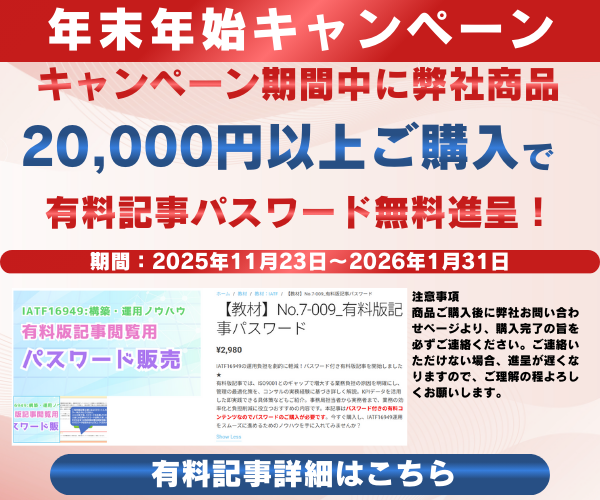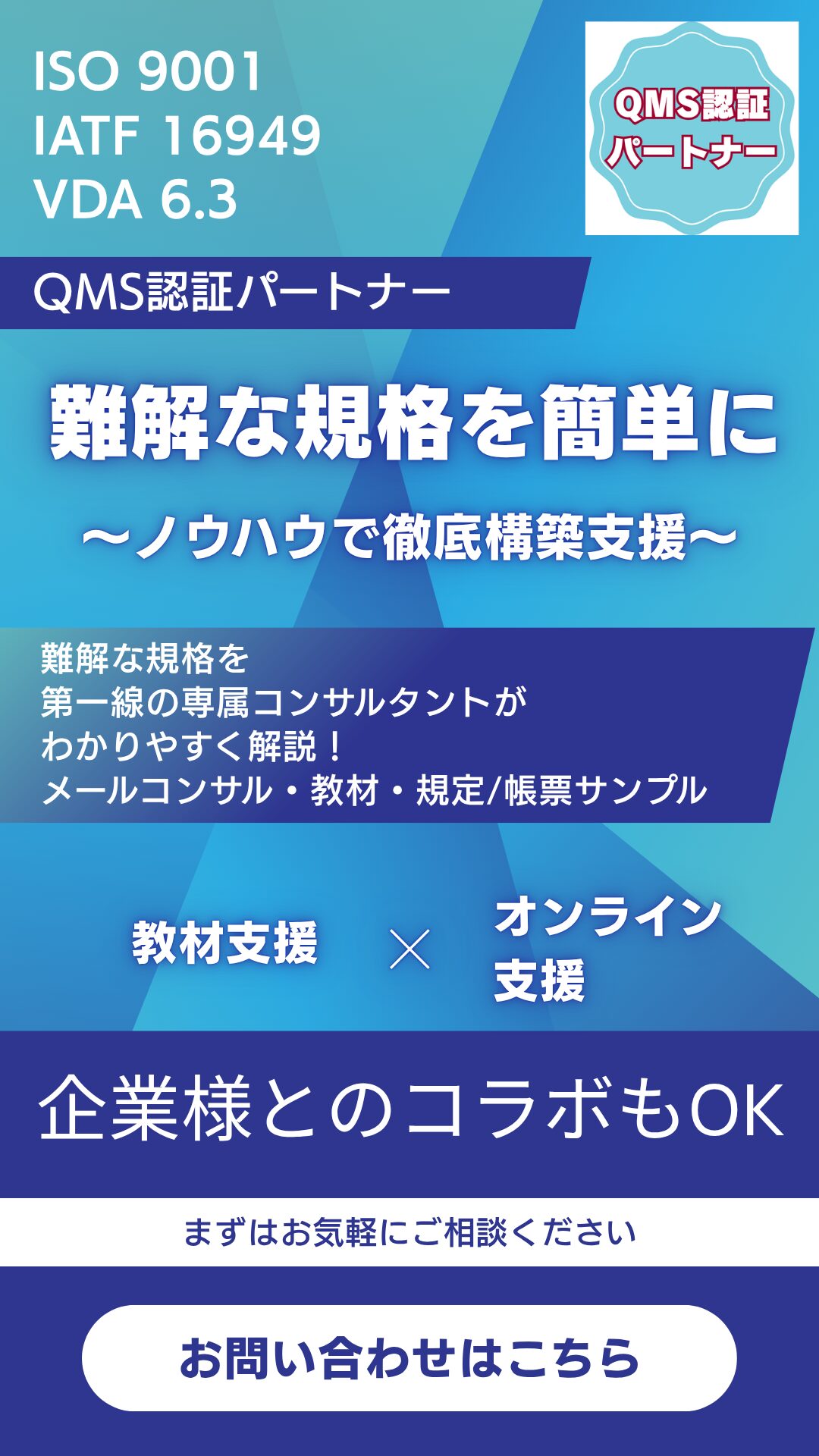製造物責任法(PL法)は、消費者が製品の欠陥による損害を被った際に、製造者や輸入者がその損害を補償する法的な責任を定めた重要な法律です。この法律は、製品の安全性を確保し、消費者が安心して製品を使用できる環境を作ることを目的としています。
PL法では、設計上の欠陥や製造過程でのミス、適切な表示がなされていない場合などが「欠陥」とみなされ、企業が賠償責任を負うことになります。
この記事では、PL法の概要や対象となる製造物、欠陥の種類、そして免責事項について解説します。

この記事を書いた人
所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
年齢:40代
経験:製造業にて25年従事(内自動車業界15年以上)
得意:工場品質改善・プロジェクトマネジメント
目標:ちょっとの相談でも頼りにされるコンサルタント
※難解な規格を簡単に解説がモットー!
【サイトポリシー】
当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。
「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!
✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ
👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!
✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ
✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む
✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック
✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ
👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!
✔ コンサルティングで具体的な課題を解決
✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入
✔ より実践的な学習教材でスキルアップ
皆様の目的に合わせて活用可能です!
| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |
ISO9001構築で整理しておきたい基本的な視点
ISO9001の構築や運用では、要求事項を理解するだけでなく、それを自社のルールや記録としてどう形にするかが重要になります。規格の意図は分かっていても、文書化や運用方法の判断で迷い、対応が止まってしまうケースも少なくありません。
まずは全体像を整理し、必要な文書や帳票の考え方を把握したうえで、自社に合った形へ段階的に落とし込んでいくことが、無理のないISO9001対応につながります。
この記事の目次
製造物責任(PL)法とは?

製造物責任法、通称「PL法」とは、製品の欠陥によって消費者が損害を受けた場合に、その製品を製造または輸入した企業や個人が、その損害を補償する法的な責任を負うことを定めた法律です。
PL法の背景
PL法の背景には、製品を使用する消費者の安全を保護するという考えがあります。たとえば、ある製品の設計や製造プロセスに欠陥があった結果、消費者が怪我をしたり、財産に損害が発生したりした場合、製造者や輸入者はその損害を補償する必要があります。
欠陥の意味が大事
欠陥とは、製品の設計、製造、表示などに問題がある場合を指します。設計上の欠陥、製造過程でのミス、適切な使用方法や危険性を知らせる表示が不足しているなどが欠陥の典型的な例です。
| 欠陥の種類 | 内容 |
| 設計上の欠陥 | 製品の設計自体に問題がある場合。たとえば、安全性を確保するための部品が欠けている、または設計時に考慮されていないリスクがある場合など |
| 製造上の欠陥 | 製品の設計は適切であっても、製造過程でのミスや不具合によって安全性に欠陥が生じる場合。例としては、組み立てミスや品質管理の不備による製品の不具合など |
| 表示上の欠陥 | 製品には表示や説明書が付属していますが、その内容が不足している、または誤った情報が記載されていることにより、消費者が製品のリスクを正しく認識できない場合。使用方法の誤りや、必要な警告表示がないことなどがこの欠陥に該当する |
これらの欠陥が原因で、消費者や第三者に損害が発生した場合、製造者や輸入者はその損害を賠償する責任を負います。訴訟においては、これらの「欠陥」が事故の原因であったかどうかが中心的な争点となるため、具体的な欠陥の定義とその判断基準の理解は極めて重要です。
PL法の真の目的
この法律は、製造者や輸入者が製品の安全性を確保することを強制し、消費者が製品を安心して使用できる環境を作るためのものです。また、事故が発生した場合には、消費者が適切な補償を受けられるようにすることも目的としています。
製造物責任(PL)法の対象となる製造物とは?

製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は、広範囲にわたる製品や商品を含んでいます。法的には、特定の利益を得るために製造され、市場に供給される「動産」を指します。
ここでいう動産とは、土地や建物などの不動産を除いた全ての動く物を意味します。日常生活で使われる家電製品、自動車、玩具、食品などが代表的な例です。特に、家電製品は冷蔵庫や洗濯機などの大型家電から、ヘアドライヤーや電子レンジといった小型家電まで多岐にわたります。また、車やバイクといった交通手段も製造物に含まれますし、玩具や食品も含まれます。
製造物責任法はこれらの製品に関して、消費者が安全に使用できることを保証するための法的枠組みとして機能します。そのため、製品を製造・販売する企業はこの法律に十分な注意を払う必要があります。
製造物責任法が適用されないケース
一方で、製造物責任法が適用されないケースも存在します。
たとえば、古物やアンティークといった中古品、あるいは個人が自作したハンドメイド商品やアート作品など、市場に大量に供給されない物は、PL法の対象外となることが多いです。これらの物品は、その性質上、製造者が意図的に消費者へ広く提供するものではないため、法的な責任の枠外となる場合があります。製造業や関連業界に従事する企業は、自社が扱う製品がPL法の対象となるかどうかを事前に確認し、適切な対応を取ることが重要です。
製造物責任法を正確に理解することで、消費者に対しての責任を明確にし、安全な製品提供を行うことが可能です。特に、製造業におけるリスク管理や品質保証の面で、PL法に基づく対応が求められることが多く、業界全体の信頼性向上に貢献します。
製造物への注意表示はどうすればいい?

製造物に対する適切な注意表示は、消費者の安全を守るだけでなく、企業が製造物責任法に基づく損害賠償を避けるためにも重要です。特に、日本の製造物責任法では、消費者が製品を誤使用した際に発生するリスクを回避するため、企業には明確で理解しやすい表示が求められます。以下では、注意表示を適切に行うためのポイントを説明します。
簡潔かつ明確な言葉で表現する
まず、製造物に表示する注意事項は、できるだけ簡潔かつ明確な言葉で表現することが求められます。消費者がすぐに理解できる言葉を選び、専門用語や曖昧な表現は避けましょう。さらに、フォントサイズや色にも注意が必要です。特に重要な注意事項は、大きく目立つフォントで表示し、赤や黄色など警告を示す色を使用すると効果的です。これにより、消費者の注意を引きやすくなります。
表示する場所も重要
次に、表示場所も重要です。製品そのものに貼り付けるか、パッケージや取扱説明書に表示するかを判断する際、消費者が必ず目にする場所に表示することが原則です。例えば、家電製品の場合は、電源を入れる前に確認する箇所や、使用中に視認できる場所に注意書きを記載すると効果的です。また、表示を一か所にまとめるのではなく、使用するシチュエーションごとに適切な場所に分散させることも有効です。
具体的なリスクについて記述する
さらに、製品に対する具体的なリスクについての詳細も含める必要があります。「高温に注意」「小児の手の届かない場所に保管」といった一般的な注意事項だけでなく、製品特有のリスクも記載することが重要です。特に、過去に起きた事故や製品の弱点に基づいた具体的なリスク提示を行うことで、消費者がより慎重に製品を取り扱うよう促すことができます。
消費者が直面する可能性のある危険を明確に伝えることで、企業側が製造物責任を問われるリスクを軽減することができます。たとえば、製品が誤使用された場合でも、適切な注意表示がされていれば、法的な責任を逃れることが可能になる場合もあります。また、消費者に対する教育の一環として、安全な使用方法を提示するのも効果的です。例えば、取扱説明書やオンラインマニュアルに、イラストや写真を用いて使用方法を説明することも、より良いユーザー体験を提供しつつ、リスクを最小限に抑える手段となります。
製造物責任を負う対象となる者の定義とは?

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって発生する事故や損害に対し、その責任者を明確にするための法律です。この法律に基づいて製造物責任を負う者は、製造者、輸入者、そして特定のブランドや商標を使用して製品を販売する者など、いくつかのカテゴリーに分かれています。
一般的な製造者
まず、一般的な製造者とは、製品の設計や生産を行う企業や個人を指します。また、自社のブランドや商標を製品に表示している場合、そのブランドを管理する主体も製造者として責任を負うことになります。これにより、消費者はブランドや製造者の信頼性に基づいた製品を安心して購入することができます。
部品製造者
次に、部品製造者についても製造物責任の対象となります。これは、最終的な製品の一部となる部品やコンポーネントを製造する企業や個人を指し、自動車業界では特に重要な役割を果たします。例えば、エンジンやタイヤなど、車両の安全性に直接影響を与える部品の製造者が、製品の欠陥に起因する事故の責任を負うことがあります。したがって、製品全体の品質だけでなく、各部品の品質も重要な要素となり、部品製造者もPL法の対象となることを理解しておくことが重要です。
関連記事
外国製品を日本国内に輸入して販売する輸入者
さらに、外国製品を日本国内に輸入して販売する輸入者も製造物責任を負います。特に製造者が海外に存在する場合、輸入者がその責任を代行する形で対応します。これは、消費者が日本国内で購入した製品に対して、適切な品質保証がなされるようにするための仕組みです。また、製品の輸入時に適切な品質検査や安全性確認を行うことで、輸入者は責任を果たすことが求められます。輸入者が製造物責任を果たせない場合、他の流通業者が責任を負う可能性もあります。
製品に特定のブランド名や商標を付けて販売する者
最後に、製品に特定のブランド名や商標を付けて販売する者も、PL法の対象となる場合があります。これは、製品に自社のブランドを冠することで、消費者に対して品質や信頼性を保証する役割を果たすためです。そのため、ブランドオーナーとしての責任が生じる場合があります。逆に、販売業者や流通業者は、製造物責任を直接負うことは少ないですが、輸入者が明確でない場合や責任を果たせない場合には、販売者が責任を負う可能性もあるため、注意が必要です。
製造物責任法の下では、消費者が製品の欠陥による損害を受けた場合に、迅速かつ適切な賠償が行われることが目的とされています。製品を製造・輸入・販売する企業は、品質管理や注意表示を適切に行い、消費者に対して安全な製品を提供する責任を果たすことが重要です。
製造物責任(PL)法により損害賠償を請求と免責事項

製造物責任法(PL法)では、製品の欠陥が原因で生じた損害について、製造者や輸入者に対して損害賠償を請求できます。具体的な例としては、以下の状況が挙げられます。
損害賠償請求ができる具体例
まず、身体の傷害や死亡が生じた場合です。例えば、家電製品がショートし火事が発生し、消費者が火傷を負った場合には損害賠償を請求できます。次に、物品の損害も対象です。たとえば、洗濯機の欠陥により衣服が破損した場合も該当します。
「欠陥」とは、製品が安全であるとの合理的な期待に反する性質を持つことを指します。これには、製造過程でのミス、設計上の欠陥、説明書や表示の不備が含まれます。このような欠陥がある場合、消費者は損害賠償を請求することが可能です。
PL法における免責事項
しかし、PL法には免責事項も存在します。まず、製品の不適切な使用による損害は、製造者や輸入者が責任を負いません。たとえば、説明書に従わずに使用した場合また、消費者に過失があった場合も免責されます。異常な音がする電化製品を使用し続けて事故が発生した場合がその例です。さらに、製造時点での科学技術では予見不可能な欠陥についても、免責される可能性があります。
PL法は消費者保護を目指す一方で、製造者側の責任が無制限ではない点を理解しておくことが重要です。
製造物責任(PL)法の制度やガイドラインはどこで入手できる?

製造物責任法(PL法)は、消費者の安全を守るための重要な法律の一つとして位置付けられています。この法律の詳細やガイドラインについては、以下のように情報を入手することができます。
製造物責任法(PL法)の詳細やガイドラインは、消費者や企業にとって重要な情報源です。これらは、主に政府機関や関連団体のウェブサイトから入手できます。具体的には、消費者庁の公式ウェブサイトが信頼できる情報提供先であり、PL法に関する最新のガイドラインや制度の詳細が公開されています。
また、経済産業省のウェブサイトでも、企業向けの解説資料や遵守すべきガイドラインが提供されています。さらに、業界団体や法律事務所が発行する解説書やセミナーも、専門的な知識を得るのに役立ちます。これらの情報源を活用することで、PL法の理解を深め、製造業や販売業におけるリスク管理や責任体制の構築に役立てることができます。
規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?
ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!
※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。
製造物責任(PL)法:まとめ
製造物責任法(PL法)は、製造業者や輸入者にとって極めて重要な法律です。製品に欠陥がある場合、事故やトラブルが発生した際に企業が責任を負うため、この法律の理解は欠かせません。
消費者の安全を守り、企業のリスクを最小限に抑えるためにも、製品の設計や製造段階での品質管理、出荷後のアフターサービスに至るまで、PL法に基づいた対策を徹底することが求められます。
製造業や輸入業に携わる全ての企業は、この法律をしっかりと理解し、実践することで信頼性の高い製品を提供していきましょう。